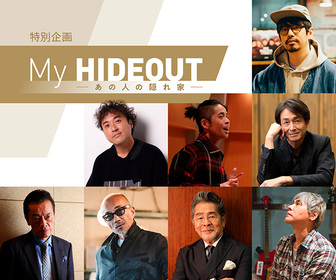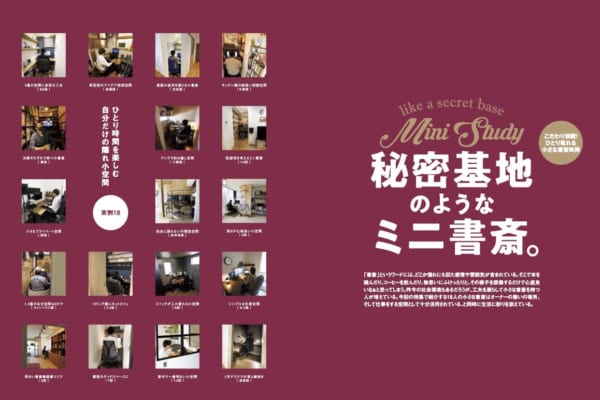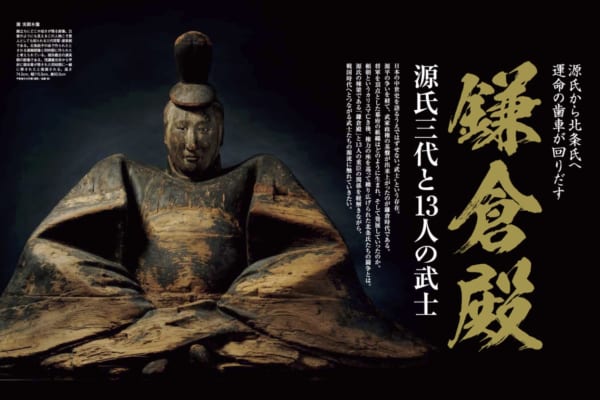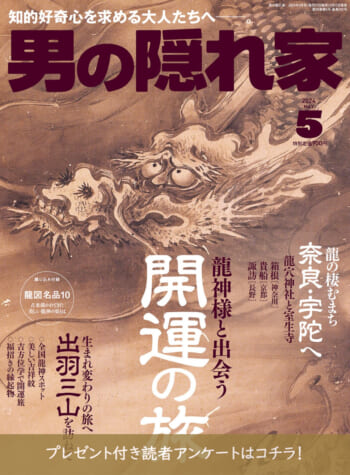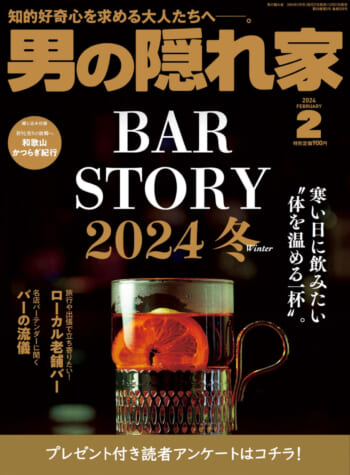どちらも味わい深く、収集の愉しみがある
伊万里は佐賀県の有田で焼かれた焼き物のことで、近くの伊万里港から出荷されたことから伊万里焼と称され、主に江戸時代に作られたものを「古伊万里」と呼ぶ。
約400年前、豊臣秀吉の朝鮮出兵の際に朝鮮半島から連れてこられた焼き物職人が、有田に窯を構えて磁器を製造。これが日本初の磁器生産とされている。
華やかな色絵もあるが、伊万里といえばやはり白地に青の文様を施した「染付」が主体。藍染の着物を思わせることからそう呼ばれ、中国の景徳鎮では同様の藍色の焼物を花に見立て「青花」と例えている。

青のもととなる顔料はコバルトを含んだ鋳物。一般的には白色の土で成形した素地(素焼)に、その顔料(呉須)で文様を描き、釉薬をかけて本焼きする。
初期伊万里はシンプルな文様が多かったが、徐々に器を埋め尽くすような唐草文、網手文なども人気に。緻密な手描きの文様は職人技の真骨頂だった。
とはいえ、そんな高価な染付の器はもともと庶民のものではなかった。しかし、明治期に入って制約が廃止されると、一般庶民向けの日常用器の大量生産も開始。その時に登場したのが「印判」という技法である。

字のごとく、いわゆる写しで「摺絵(ずりえ)」「転写」などの方法がある。摺絵は文様を彫った型紙を器面にあてて、刷毛などで絵具を付着させる方法。
転写は銅版を使ったエッチングと同様の技法で、顔料も“ベロ藍”というものを用い鮮明な発色が得られるようになった。印判は肥前で明治初期に手がけられ、その後、美濃や砥部など全国の磁器生産地に広がっていくことになる。
染付と印判の見分け方はまず値段に反映されており、またよく見てみると印判は文様のズレや擦れなどがある場合もある。しかし、明治・大正期の古い印判はそれも味わいとして人気があるのだ。骨董店に指南を仰ぎ、それぞれの魅力を知って使い分けてみるのも面白いだろう。
文/高地 梓