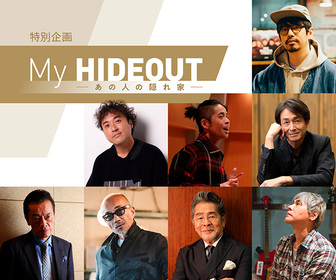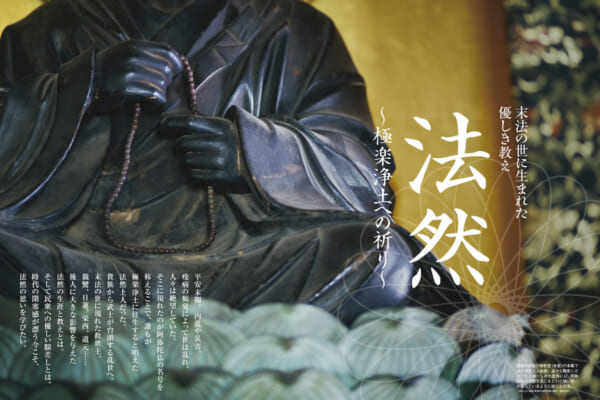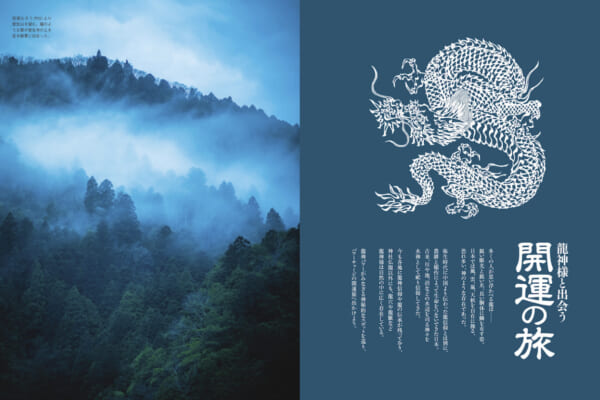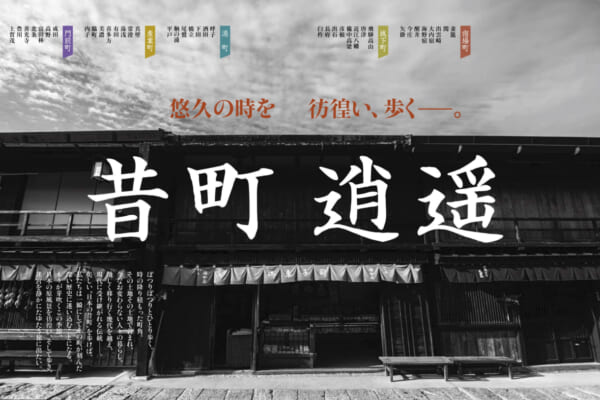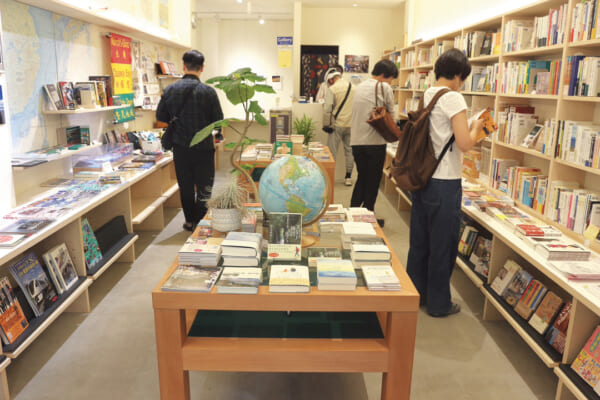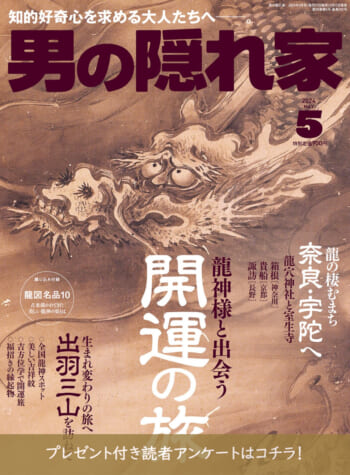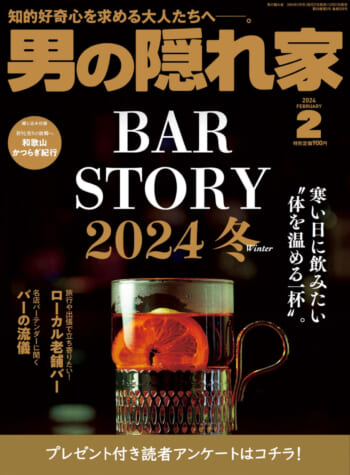■海外ではサイレントキラーとも呼ばれている!?

東京消防庁が発表した過去5年間の「餅などに起因した窒息事故による救急搬送」のデータを見ると、毎年100人ほどの人が病院へ運び込まれているという。さらにそのうちの6〜7%が残念ながら初診時に死亡が確認されている。また、搬送者の内訳を年齢別で見ると65歳以上の高齢者が90%ほどを占めているのは、大きな特徴だといえるだろう。
そういった日本で毎年起こる「餅を喉につまらせる事故」が海外のニュースメディアで「サイレントキラー」と伝えられ、外国人の読者の中で話題となることもしばしばである。
海外の人からすると「どうしてそんな危険な食べ物を食べるのか?」「なぜ規制しないのか?」という不思議がる意見がある一方で、「日本古来からの風習や文化なら尊重すべき」という声もある。
また、こちらの記事で紹介したように「雪見だいふくのようなスイーツ」として認識する人々も増えている。
■そもそも、どうして正月に餅を食べるのか?

実際のところ“正月に餅を食べる日本人”ならではの習慣の起源について、諸説あるものの“これ”という正解はない。“いつから・なぜ”食べ始めたのか、という記録が実は残っていないのだ。
しかし正月飾りの一つ「鏡餅」に関しては、平安時代の源氏物語に記された「歯固めの祝ひ」(硬いものを食べて健康を願う儀式)で鏡餅という単語が登場し、この頃にはすでに「お祝い」や「お供え」のアイテムとして存在していたことがわかる。
では単純に餅はいつから存在するのか探ってみると「弥生時代には稲作信仰により食べていた」という説があるが、少なくても奈良時代の豊後国風土記には餅を作っていた記録が残っており、どちらにせよとても古い時代から日本人は稲作をして米を作り、餅にして食べていた。
また、日本人のライフ・イベントと照らし合わせてみると、さまざまなタイミングで餅が登場するのがわかる。
・お食い初めは「歯固めの祝ひ(儀式)」が起源
・初誕生日(1歳)で風呂敷に包んだ一升餅を背負わせる
・端午の節句には柏餅をお供え
・ひなまつりには菱餅を飾る
・家を建てる時、棟上式で餅を撒く
このことから餅は縁起物として古くから大切に食べられてきた、いわば日本人のソウルフードだといえるだろう。
■大晦日の儀式にヒントがある?

大昔の日本人は「元日に神様が来る」ことを信じていたため、その前日にあたる大晦日には神様へのお供えとして餅や魚などの食べ物を用意していたという。そして、そのお供えを元日に神様と共にありがたく食していた。
やがてその習慣が時代を経て「お雑煮」になったのではないかといわれている。なお、室町時代の鈴鹿家記に「雑煮」という単語が初めて登場するが、実際にはこれより前から食べられていたのは間違いないだろう。
このように稲作信仰で発展した日本ならではの食品「餅」は、古来から「ハレの日」には欠かせない縁起の良い存在として私たちの人生に欠かせないものとなっている。
近年では正月に餅を食べないという人も増えているが、一年が始まる元日や松の内が明けた1月11日の鏡開きには、美味しく餅を食べて縁起の良いスタートを切りたいものだ。