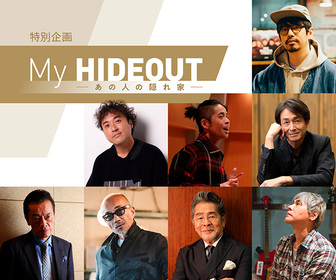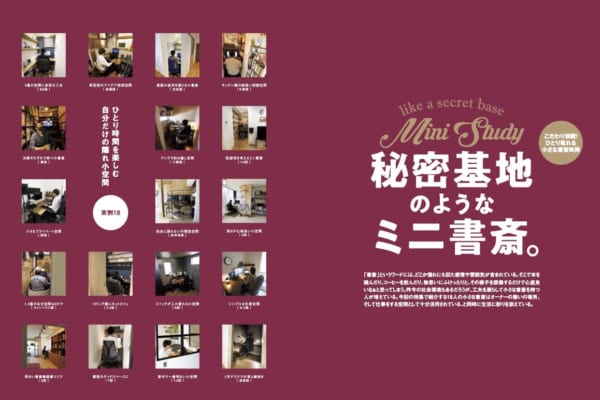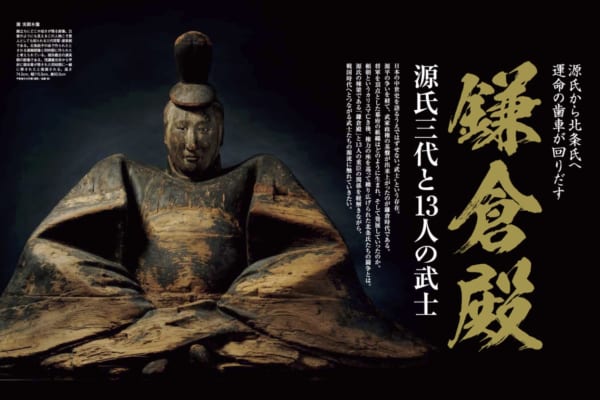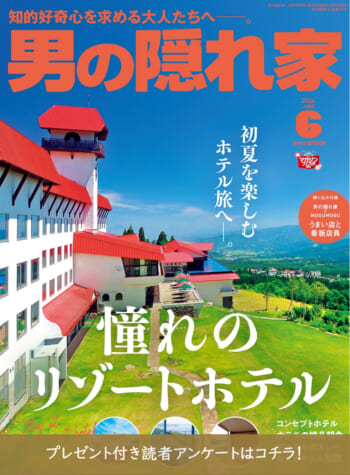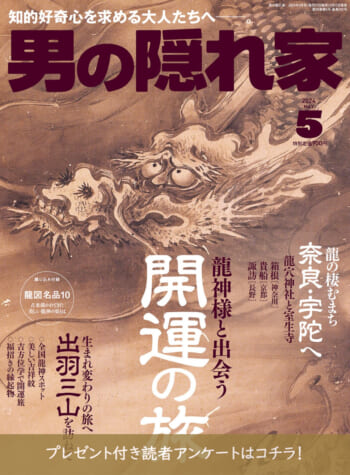金山城(かなやまじょう)
築城年:文明元年(1469)
主な城主:宇津木氏久
威圧感のある石垣と縄張りを楽しみながら散歩をする

関東平野の北端に位置する標高239mの独立丘陵・金山に築かれた中世を代表する山城。文明元年(1469)に新田氏一族の岩松家純の命により築城され、上野(こうずけ)、下野(しもつけ)、武蔵を結ぶ要衝にあったため、戦国時代には覇権争いの舞台となった。

自然地形を生かした堅牢な造りは難攻不落の城として名を馳せ、越後の上杉氏、甲斐の武田氏など有力戦国大名に挟まれながらも、一度も城の中枢まで攻め込まれなかったという。

金山山頂にある本丸(実城・みじょう)を中心に、北方の北城、西方の西城、南方の八王子山ノ砦など4つの核があるが、駐車場近くの西城から物見台虎口、そして要塞のような大手虎口周辺までの気持ちの良い散策路を歩くだけでも十分だ。



散歩気分で山を登り本丸へと続く大手虎口へ
金山城は平成7年(1995)から発掘・復元整備が行われた。往時の遺構をリアルに体験できる数少ない山城のひとつだ。登城への道も整備され、攻める側、守る側の視線で山城歩きを楽しむことができる。

ハイライトは石垣の連なりが圧巻の大手虎口や円形の貯水池。いずれも関東の山城では珍しい石積みが美しく施され、再現されたものとはいえ迫力満点だ。


【こんな所も見どころ!】
金谷城の北部に残る丸山宿道中央の水路に往事の生活を偲ぶ

金山城の北側に約500mに渡ってひっそりと昔の風情を残す丸山宿。この地(現・太田市)の出身で江戸中期の尊王思想家・高山彦九郎の日記『小俣行』にも記されている宿場町で、黒塀や蔵のある屋敷のほか、道中央に往時を偲ばせる水路が残っている。