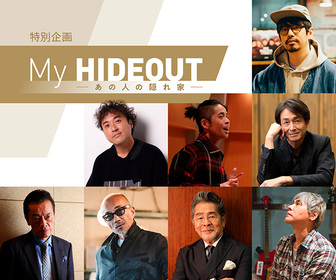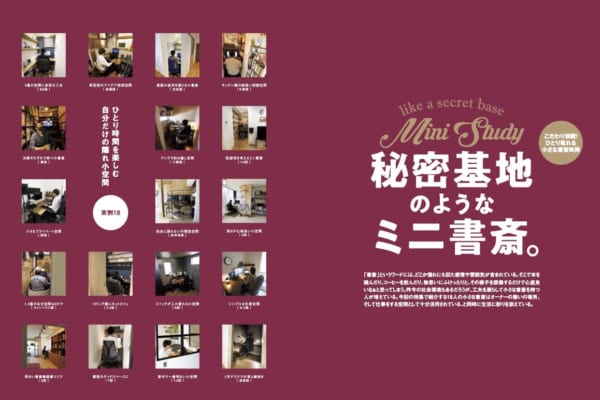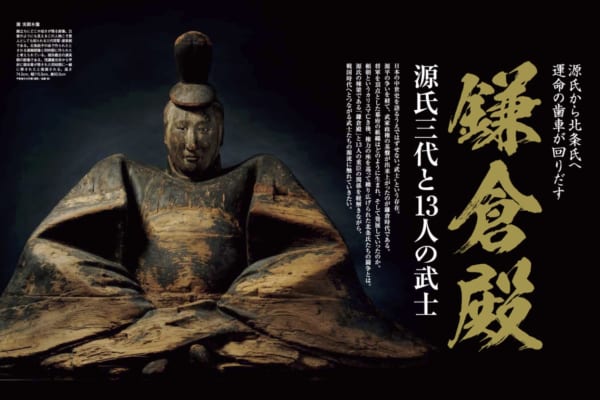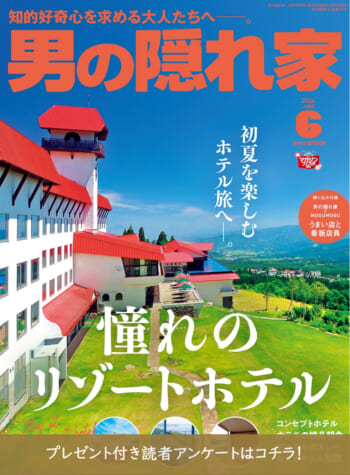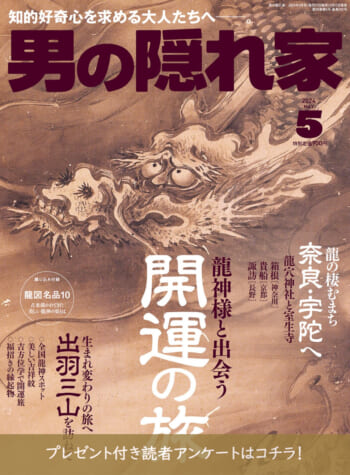目次
鮮明な古写真や木組模型など、豊富に残された再建の史料
城としての始まりは、鎌倉時代末期、伊予国守護・宇都宮豊房の築いた地蔵ヶ岳城といわれる。近世初頭に大洲の地を治めた小早川隆景をはじめ、築城名人として知られる藤堂高虎や加藤貞泰ら各大名たちの造営を経て、近世城郭として整備されていった。

元和3年(1617)以降は加藤氏が大洲藩主となり、十三代にわたり居城とした。江戸時代、火災や地震に見舞われ櫓類が崩壊するも、その都度再建された。その後、明治6年の廃城令により城内の建造物は破却されるも、天守と櫓は保存される。しかし明治21年(1888)に老朽化を理由に天守は解体されることとなった。

城を大切にしていた市民の働きかけもあり、市制施行50周年記念事業として天守の復元が実現。復元には江戸時代の古絵図や江戸時代の棟梁が作成したとみられる天守雛形、明治時代に撮影された古写真が用いられた。

慶長期の天守を再建するため全国の職人が招集され、木組みや漆喰、瓦にいたるまで当時の工法を再現。天守に附属する台所櫓をはじめ、江戸期から現存し国の重要文化財に指定されている高欄櫓、櫓、三の丸隅櫓と共に、市民に愛される名城の威容を誇っている。
おおずじょう
築城年/元弘元年(1331)
廃城年/明治6年(1873)
構造/梯郭式平山城
主な城主/宇都宮氏、藤堂氏、脇坂氏、加藤氏
遺構/台所櫓、三の丸南隅櫓、本丸井戸、内堀跡など
写真/大洲城管理事務所